即断即決
順調なときは放っておいていいが、逆の場合はそうはいかない。わたしは、自分の購入した株が思惑からはずれた場合、すぐに処分するようにした。間違った方向への値動きが始まると、どうしてだろうとだれもが原因究明に乗り出したくなるものさ。しかし、最も重要なのは「その時点での状況」だ。すでに判断の間違いに議論の余地はないのだから、老練な相場師なら即座に手じまうだろう。
引用元:リチャード・スミッテン 藤本直(訳)(2001)「世紀の相場師 ジェシー・リバモア」角川書店
利益の出ている取引は放置しておいてよいが、損が出た場合は即断即決が必要だ。
よくある話だと思いますが、「エントリー後、すぐ逆方向に動かれて損切り貧乏になる」という経験をされた方は多いのではないでしょうか。私はその経験があります(笑)。
ジェシーの言いたいのはそのようなことよりも、例として、上昇トレンドと判断していてロングポジションを持っているときに下降トレンドに転換しているのではないかと考えたときの思考や行動です。
私はその時間足でのトレンドの目安として中期移動平均線(20期間前後)という話をブログでもよくしていますが、エントリー後、逆に動かれたとしても依然として中期的な動きとしてそのトレンドや方向性に変化が見られないのであれば、耐えて戻ってくるのを待つようにしています。
精神的にはエントリー後すぐ逆に動かれてしばらく含み損を抱える状態になってしまうのはしんどいですが、変化がなければそこは耐えなくてはいけません。耐えられない場合に限って損切り貧乏になってしまいます。
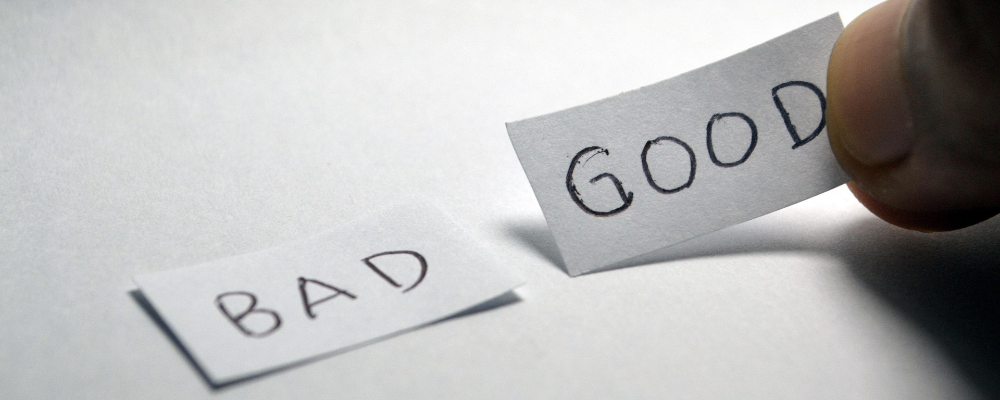
だからこそ、中期的な状況判断というのはとても大事で目先の動きにとらわれることなく、トレンドの判断基準を自分なりに決めておくことが基本であり、重要です。そして、自分の思っている形やルールと違ってきたり、相場に変化が見られるまではホールドし、変化が見られたら手仕舞うべきという思考に持っていかなければなりません。
また、レンジ相場において、中期移動平均線が平べったい横向き状態でそれを挟んでの動きの中で中期移動平均線付近からエントリーするのは好ましくありません。これも精神的に願望が入ったり、バイアスがかかったりしやすくなる場面でもありますし、判断が手詰まりな状態に陥り、手仕舞いのタイミングが難しくなります。
利益が出ている時はとにかくできるだけホールドし、イメージと違ってきたり、チャートの形が悪くなってきたと思えたら冷静に判断し、早めに決済するという意識も常に準備しておきましょう。
トレードにこだわりを
わたしは、一度ルールを決めたら、それを守り通そうする決意、姿勢が極めて重要と思っている。明確で具体的、立証済みのルールをもたない相場師が、偶然でない成功を実現させるのは絶望的だ。なぜかというと、投資計画の全体像が見えていない相場師は、戦略をもたない。つまり実行可能な戦術をもたない将軍と同じだからだ。筋の通った明確なプランをもたない投資家たちは、その場その場の状況に反応し、右往左往する。市場のあらゆる方向から飛んでくる矢玉に対応することができず、結局大損を被り、去っていくわけだ。
引用元:リチャード・スミッテン 藤本直(訳)(2001)「世紀の相場師 ジェシー・リバモア」角川書店
私のマイルールであるキャッチライン(15分足の21EMA、MTF1時間足の5SMA/5EMA)を利用したトレード方法はもう何年も変わらず、こだわり続けている手法です。ただ、それぞれの場面でトレードするかどうかの選択肢は臨機応変にトレードするようにしています。つまり、マイルールに合致したとしてもマイルールに優位な場面なのかそうでないのかという判断もするようにしています。その判断方法はチャートの形であったり、インジケーターの情報であったりします。
エントリーのルール、手仕舞いのルール、相場のその時の状況において臨機応変なルール、マネーマネジメント、リスクコントロール、チャートパターンやインジケーターから見える状況、これらのルール基準を考え、それに基づいて、それにこだわり続けてトレードすることが大切だと思っています。
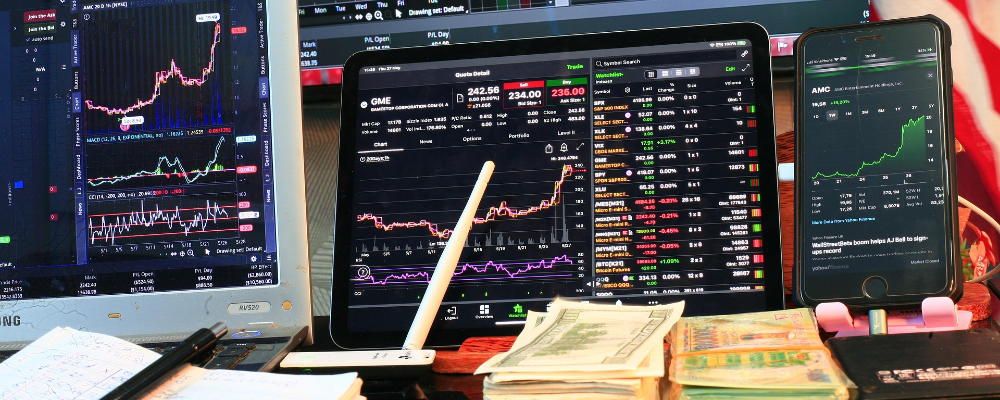
そうすることによって、正解というものはありませんが、確率的に優位なものかそうでないのかということを自分が納得できる正しいトレード方法に導けるようにルールにこだわってトレードすることは大切だと思います。
こだわる=チャートやインジケーターの特徴や見方を理解し、それを相場の判断方法に活かせる場面を想像し、理解できているからこそこだわることができるのだと思います。
もし、自分でなにか欠けているものがあればほったらかしにせず、一つ一つ解決しながらルールを決めてみましょう。
また、ルールというのはチャートの規則的な動きや形が何を意味しているのかを理解し、それによってトレンドや反転のシグナルを見極めるという意味もあります。
バイアスがかからないように
ジェシーのネタもこれが最後です。私自身、初心を忘れないように振り返りながら先人から学べたことがたくさんあります。皆さんにもお役に立てていたならうれしく思います。
わたしは「ブル(強気)」とか「ベア(弱気)」といった相場用語を絶対口にしないようにしている。こういった表現を使うと、言うほうも言われる方も、相場の先行きについて固定観念を抱くことになるからだ。相場を張る者の心の目が曇ると言ってもいい。その言葉の魔術に惑わされ、いつの間にか長期的に、たとえ市場の状況が変わってもなお、その言葉の示す方向、トレンドに従っていたりすることになる。
引用元:リチャード・スミッテン 藤本直(訳)(2001)「世紀の相場師 ジェシー・リバモア」角川書店
(中略)だから、市場の現状を聞かれた場合、現在は「上向きのトレンド」にある、「下向きのトレンド」にある、「横ばいのトレンド」にある、などの言い方で答えている。「最小抵抗ラインは上を向いている」あるいは「下を向いている」などの言い方もする。しかし、それ以上のコメントはしない。
そうすることで私自身の頭脳、考え方に柔軟性が維持されるから、相場の変化に用意に追随していけることになる。それからわたしは、株価の先行きを洞察しようとか、予想しようとか思ったことは一度もない。わたしはひたすら、市場が自らの振る舞いを通じてわたしに伝えてくれる情報に対応していくだけだ。
トレーダー仲間と「相場は今どんな感じに見えますか?」みたいな話をするときに「私はまだ上方向に行くと思っている」「私は下」というような会話がたまにあります。
それに対して私はマイルールを元に現状をどう見ているか、その理由を説明するにとどめ予想は話しません。
これはジェシーの考えを真似したわけでもなく、たまたまジェシーと同じ考え方で他人に自分の予想などを話してしまうとそれに対してバイアスがかかったり、身動きが取れなくなるとわかっているからです。
また、私のような話に同調して真似されて失敗されても責任は取れず、自分の責任とは思いたくありませんが、それでも少し申し訳ない気持ちになってしまいスッキリしない結果になってしまうことがイヤだということもあります。
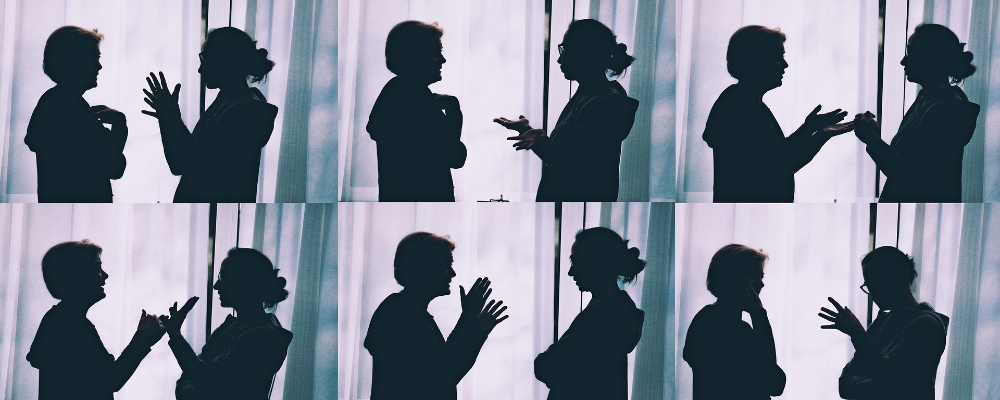
どのアナリストやネット上からの意見も単純に真似するのではなく、その人の相場観やその人に対しての信頼度など、納得してから自分の責任においてトレードしましょう。
トレードの話を友達や誰かと話をするときにそれが自分に対してプレッシャーになるような言い方は決して良いことではありません。それがいつまでもバイアスとなってしまい、普通なら損切りしているような場面や利確するような場面で「まだまだ行ける」などと言って損切りできずに含み損が増えてしまったり、儲け損ないが大きくなる可能性もあります。
つまり、誰との会話ということだけではなく、予想を立てることによって逆効果になる場合もあるということ、そして、バイアスをかけてはいけない場面というのをちゃんと理解しながらポジションメイクすることが大切だと思います。
そして、常に淡々と冷静に自分自身がトレードできるような環境も大事です。他人がどう言おうと自分の考え方や判断を信じる「もの」が必要になります。他人の意見はあくまで参考程度に聞き、自信がなくても自分の判断が他人に左右されることのないようにスキルアップをしながらトレードを楽しみましょう。
他人がその相場をどう評価しようが、自分の判断が意義のあることだと考え、トレードに対して深い思い入れをすることが大事です。
Copyright ©fc2blog: 2020-10-29, 2020-11-03, 2020-12-02